夏井 いつき(なつい いつき)さんについて、プロフィール・経歴・家族・活動内容などをまとめます。

目次
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前(ペンネーム) | 夏井 いつき(なつい いつき) (ウィキペディア) |
| 本名 | 加根 伊月(かね いつき) (ウィキペディア) |
| 生年月日 | 1957年5月13日 (ウィキペディア) |
| 出身地 | 愛媛県南宇和郡内海村(現・愛南町) (ウィキペディア) |
| 居住地 | 愛媛県松山市 (natsui-company.com) |
| 最終学歴 | 京都女子大学 文学部 国文科卒業 (ウィキペディア) |
| 元職業 | 中学校国語教諭(松山市立余土中学校・御荘中学校など)8年間 (ウィキペディア) |
経歴・活動
- 教員として国語を教えていたが、1988年に教職を辞し、俳句の道へ転身。 (ウィキペディア)
- 黒田杏子に師事。 (ウィキペディア)
- 1994年、第8回「俳壇賞」を受賞。 「俳壇」という俳句界での権威ある賞のひとつ。 (ウィキペディア)
- 「いつき組」という俳句集団を作り、組長として活動。 (ウィキペディア)
- 「句会ライブ」の開催、全国高等学校俳句選手権「俳句甲子園」の創設など、俳句を若い世代に広める教育的活動にも力を入れている。 (ウィキペディア)
- メディア出演:テレビ番組『プレバト!!』(俳句コーナー)、NHK「NHK俳句」、その他テレビ・ラジオ・講演などで活躍。 (WEBザテレビジョン)
- 社会的活動として「俳都松山宣言」の初代「俳都松山大使」に就任。松山市を拠点にし、俳句文化の普及を図っている。 (ガイドと行くまちあるき『松山はいく』公式サイト)
家族・私生活
特徴・作風
- 季語を使った定型俳句(五七五)を重視しつつ、「感じたままを表現する」という自由な句作も評価されている。 (ウィキペディア)
- 辛口ながらも暖かさがある評価者として知られ、特に『プレバト!!』での俳句添削での鋭い指摘が注目される。 (ウィキペディア)
- 「俳句は才能ではなく筋トレ」という言葉を用い、誰でも挑戦できるものとして俳句を普及させたいという信念を持っている。 (ほぼ日)
主な受賞歴・著書等
- 主な受賞歴:俳壇賞(第8回)など多数 (ウィキペディア)
- その他受賞:第44回放送文化基金賞、NHK放送文化賞、種田山頭火賞など (natsui-company.com)
- 著書多数、『伊月集』『絶滅寸前季語辞典』などの句集・季語辞典・俳句入門書を執筆。 (ガイドと行くまちあるき『松山はいく』公式サイト)
夏井いつきさんの「有名な句(ベスト句)」と、「プレバト!!」で語った/言われた名言・エピソード、覚えておきたいポイントをいくつかまとめます。
有名な句・ベスト句から
「伊月集 梟(ふくろう)」など、句集やファンによって特に評価されている句の中から、以下のような句が挙げられています。感覚を捉えるのにいい例です。(note(ノート))
- ふくろうに聞け快楽のことならば ― 快楽の「ことならば」を呼びかけのようにして、ふくろうという静かな、夜の象徴的生き物を通して詩的な問いを投げかける一句。(note(ノート))
- 冬鴫の脚きんいろに折れそうな ― 冬の鴫(しぎ:水鳥の一種)の細くて冷たい脚に「折れそうな」様子を重ねて、自然の脆さ・儚さを感じさせる句。(note(ノート))
- 箱庭に濡れたる月のあがりそう ― 箱庭という小さな場所に湿り気があり、そこに月が昇ろうとしている情景を、静かに、美しく想像させる一句。(note(ノート))
これらの句はいずれも、五七五の中で季語を使いながら、描写と比喩・余韻で読者に想像を引き起こす力が強いものとして評価されています。(note(ノート))
プレバト!! での名言・エピソード
夏井いつきさんが「プレバト!!」などで語ったこと、また出演者が彼女について語っている言葉から、“俳句を詠むこと・教えること”に対する考え方がよく表れているものをいくつか紹介します。(note(ノート))
| 名言・発言 | 内容の要点 |
|---|---|
| 「俳句には、人を変える力がある。」 | ただの趣味や表現活動ではなく、俳句づくりを通して人の考え方・感じ方・生き方が変わるという見方。(心を輝かせる名言集) |
| 「俳句は人生の杖になる」 | 困難や苦しさに対して、俳句を作ること・表現することが支えになるという思い。(koubo.jp) |
| 「実力がない人に限って格好いい言葉を使いがち」 | 才能ナシと判断される俳句には、言葉の “見せかけ” が強いものが多い。内容との整合性や、言葉の選び方・使い方の深さを重視するという批評。(エキサイト) |
| 句の添削で、「“写っているもの”だけでなく、“写っていないものを想像すること」 | 写真・お題から俳句を作るとき、見たものだけでなく、その空気・余白・見えない部分を感じ取ることが句に深みを与えるという指導。(婦人公論.jp) |
| 所属の句で「金秋戦」の予選Aブロックで、「添削なし」の名句が続出→「皆さん素晴らしいじゃないですか!」 | 自分が期待していた以上に、句の完成度が高い作品が集まり、添削不要と感じるほどだったという評価。泣き言ではなく、みんなが想像力を発揮しているという喜び。(MBS 毎日放送) |
覚えておきたいポイント
- 夏井いつきさんは、俳句を「型(五七五・季語)」という制約の中で、その中から何をどう表現するか、想像力と感性を働かせることを非常に重視しています。(koubo.jp)
- 初心者にも“まず作ってみる”“型を怖れずに使ってみる”ことを勧めており、「センスだけではなく継続が大事」であるという考えがしばしば語られています。(koubo.jp)
- また、言葉選びの丁寧さ、誤魔化しのない描写、そして感情を託す余白のある表現を重視する。わかりやすい言葉でも “本当に見た・感じたもの” が句に宿る句が高く評価される。(婦人公論.jp)
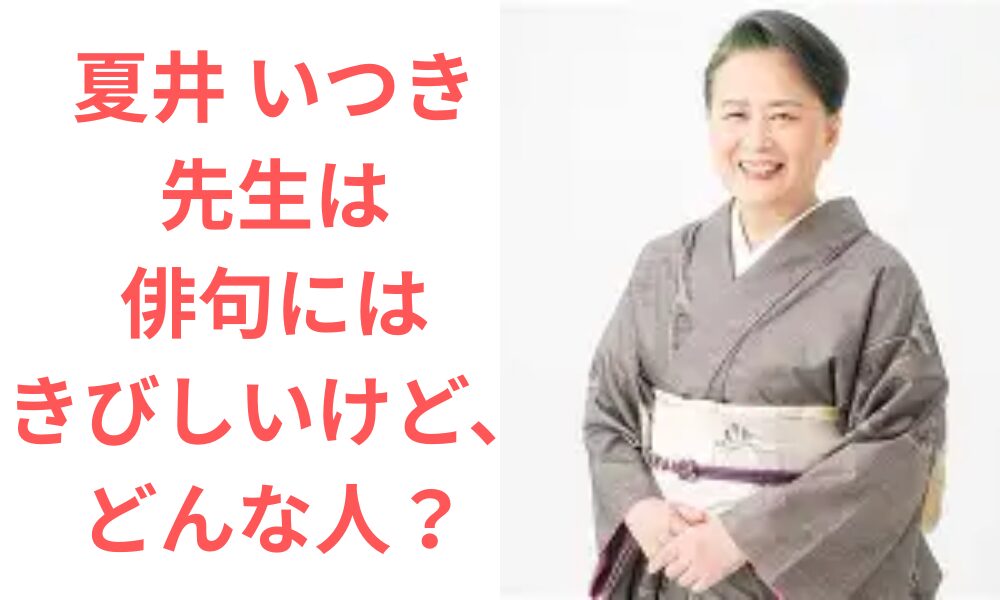
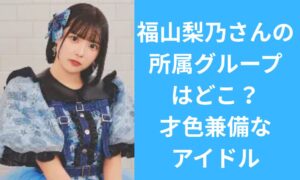
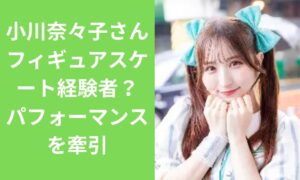
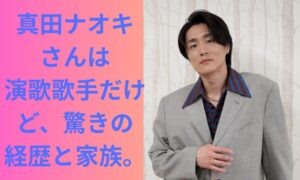
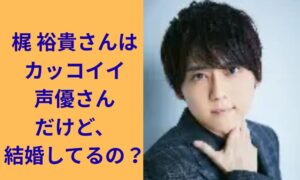

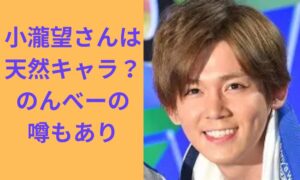
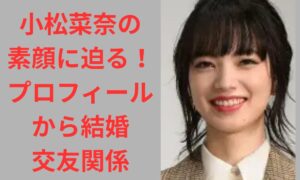

コメント